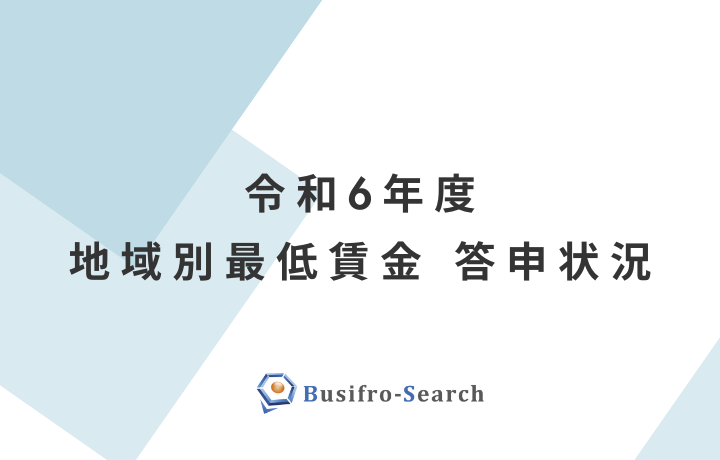【2025年最新版】入社祝い金の禁止ルール|企業と求職者が知るべきポイント

かつては「入社祝い金○○万円支給!」といった求人広告を目にする機会が少なくありませんでした。特に人手不足の業界や職種においては、こうした金銭的インセンティブによって求職者を惹きつける手法が広く使われてきました。
しかし、2021年4月1日以降、職業紹介事業者(いわゆる転職エージェントなど)による入社祝い金の提供は原則禁止となり、さらに2025年4月1日からは、募集情報等提供事業者(求人サイトなど)にも同様の規制が適用されました。
この記事では、入社祝い金がなぜ規制されるようになったのか、その背景と狙い、そして求職者や企業が今後注意すべきポイントについて解説します。
入社祝い金とは?
入社祝い金とは、求人企業や職業紹介事業者、求人サイトなどが、求職者に対して採用や入社が決定した際に支給する金銭や商品券等の報酬のことを指します。
その目的は、応募者を増やしたり、求職者の選考意欲を高めたりすることにありました。特に有効求人倍率が高く、人材の獲得競争が激しい業界(例えば介護・飲食・物流など)で多く見られていた施策です。
なぜ入社祝い金は原則禁止になったのか?
1. 求人市場の健全化を目的とするため
入社祝い金は一見、求職者にとって魅力的な制度に思えるかもしれませんが、本質的なミスマッチを助長するという問題点があります。
求職者の中には、業務内容や就業環境を十分に検討せず、「祝い金がもらえるから」という理由だけで就職を決めるケースが増えていました。その結果、早期離職が多発し、企業も求職者も互いに損失を被る事態が発生していたのです。
2. 転職の“連鎖”を引き起こす温床に
職業紹介事業者の中には、企業から受け取る紹介手数料を複数回得るため、すでに紹介した人材に対して再び転職を促すようなケースが実際に報告されています。
例えば、一度紹介して入社させた求職者に対し、「次に転職すればさらに入社祝い金がもらえますよ」と持ちかけて短期間で退職を促すという行為です。
こうした「転職ビジネス化」は、本来あるべき就職・転職の目的とはかけ離れており、業界全体の信用失墜にもつながりかねません。
3. 求職者が金銭目的で応募を決めてしまう
「入社祝い金○万円支給」のような広告は、祝い金の額で求人を比較することを助長します。
たとえば、業務内容や勤務地、社風などを十分に理解せず、「一番祝い金が高い求人に応募する」という判断をする求職者が増えてしまいがちです。これは、企業にとっても求職者にとっても不幸な結果を招きやすく、採用活動の質を下げる要因とも言えます。
禁止の対象となる行為とは?
厚生労働省が定めるガイドラインによれば、入社祝い金の原則禁止は**「社会通念上相当と認められる程度を超える金銭等の支払い」**を対象としています。
以下のようなケースが、禁止の対象に該当します。
- 数万円〜数十万円単位の現金を入社時に支給する
- 高額な商品券や図書カードを提供する
- 入社直後に特典として旅行券や高価な物品を贈る
なお、金銭だけでなく金券や物品なども含まれるため、「現金じゃなければOK」というわけではありません。支給のタイミングや内容に関係なく、「社会通念上の範囲を超える」と判断されれば規制対象です。
今後、企業と求職者が意識すべきこと
■ 求職者側のポイント
今後は「祝い金があるから応募する」という動機は通用しなくなります。代わって、仕事そのもののやりがいや企業の文化、将来的な成長性などを軸に企業を選ぶ意識がますます重要になります。
また、「祝い金がある」と謳っている事業者があれば、その時点でガイドライン違反の可能性があるため、慎重に対応しましょう。
■ 企業側のポイント
企業としては、金銭的なインセンティブではなく、職場環境や働きやすさ、キャリアパスなど“中身”で勝負する姿勢が求められます。
また、求人広告の内容についても法令順守が厳しく問われるようになってきているため、職業紹介事業者や求人サイトとの連携においてもコンプライアンスの観点を重視する必要があります。
まとめ
入社祝い金の原則禁止は、「金銭で釣る採用」から脱却し、より健全でミスマッチの少ない雇用を実現するための一歩です。
企業にとっては“人材の定着”が重要課題となっており、求職者にとっても“長く働ける場所”を見つけることが何より大切です。祝い金の有無ではなく、自分に合った職場かどうかを見極めることこそが、満足度の高い就職・転職の第一歩と言えるでしょう。