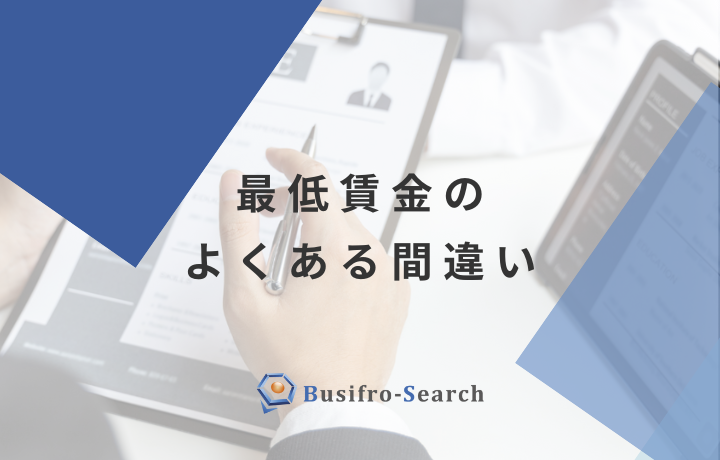【前編】2026年の労基法“全面見直し”で変わる10のポイント|人事・労務が今から備えるべきこと

はじめに
●2026年に向けた「労働基準法改正」の意義
近年、働き方の多様化、テレワークの普及、複業・副業の拡大、そして高齢化・少子化の進展にともなう労働力構造の変化など、わが国の雇用・労働環境は急速に変貌を遂げています。こうした状況を背景に、厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」では、現行の労働基準法(以下「労基法」)が、こうした新しい働き方・働く実態を十分にカバーしていないとの認識から、制度の抜本的な見直しに向けた議論が進んでいます。
報道等では、「40年ぶりの大改正」とも言われており、企業側・労働者側ともにその影響が大きなものになると予想されています。
本稿では、改正検討案として浮上している10の主要論点を整理し、それぞれの意義・解説・実務インパクトとともに、今後の備えとしての視点を整理します。
改正検討案10選
以下では、検討が進んでいる改正案を「1.~10.」の形式で個別に整理します。なお、今後の法案化・施行時期・内容には変更の可能性がありますので、あくまで“検討段階の論点”としてご覧ください。
1.連続勤務の上限規制(14日以上の連続勤務禁止)
第1の検討案は、現行の労基法において、「4週間を通じて4日以上の休日を付与すればよい」という特例(4週4日休日制)を適用した場合、理論上は最長48日間もの連続勤務が可能になる実務運用の問題を踏まえ、14日以上の連続勤務を禁止するという上限規制の導入です。
背景と意義
- 長期連続勤務が、過労・ストレス・疲労蓄積・メンタル不調のリスクを高めることが、労災認定の現場でも指摘されています。実際、精神障害の労災認定基準には「2週間以上の連続勤務等」が目安として取り上げられています。
- 48日連続という数字は、現行の規定にもとづく理論値であり、実態的にこのような長期無休日勤務が生じているケースも散見されます。労働者の健康確保という観点から、連続勤務日数の上限を法的に定める意義があります。
- 働き方改革以降、「働きすぎ」防止・健康確保が重要なテーマとなっており、本案はその延長線上に位置づけられます。
検討内容
- 具体的には、「連続14日以上の勤務を禁止」「2週間2日休みを確実にする仕組みに変更」「4週4日から2週2日など変形休日制の見直し」などが検討されています。
- あわせて、変形労働時間制・交替制勤務・シフト制勤務など、休日取得パターンが複雑な事業場における運用ルールの明確化が求められています。
実務インパクト・留意点
- 企業側では、シフト設計・休日設定・勤務表の作成において、「14日以上連続勤務になっていないか」を常時チェックする体制が必要となります。
- 就業規則・勤務規程・就業管理システムの見直しも必須です。特にシフト制・変形勤務制を採用している事業場では、制度設計の段階から詰めておく必要があります。
- 労働者側にとっても、休日がしっかり確保される方向となるため、健康・生活リズムの確保という点で歓迎できる内容です。ただし、シフト確定のタイミング・休暇申請・交代出勤の対応など、柔軟な運用とのバランスが課題となる可能性があります。
- ただし、本案が成立・施行される時期・具体的数値(14日か13日か)・変形休日制の枠などは、今後の議論で変わる可能性があるため、動向を注視する必要があります。
2.法定休日の特定義務化
第2の検討案は、現行法において「法定休日(=使用者が少なくとも週1回与える義務のある休日)」を具体的に「どの日が法定休日か」を特定する義務がないことを問題視し、これを制度的に強化するというものです。
背景と意義
- 法定休日か法定外休日かによって、休日労働時の割増賃金率や代休制度の適用が異なりますが、事業場によって「どの日が法定休日か」が明示されていないケースがあります。これがトラブル・リスクにつながるとされています。
- シフト制や変形労働時間制、交替勤務制といった勤務の多様化が進んでいるなか、休日の特定をあいまいにしておくことのリスクが増しています。
- 労働者の休日の確保・私生活との調和を図る観点から、休日制度の透明化・明確化が図られるべきという観点もあります。
検討内容
- 企業は「法定休日を事前に特定する」ことを義務化される見込みです。例えば、就業規則・勤務規程上で「毎月第○日」「毎週○曜日」など具体的に法定休日を示す。変型的なシフトの場合でも、勤務表・シフト表等で「本週の法定休日は○日/○曜日」というように示す。
- 法定休日の振替・代休制度・休日の変更手続きなどをあらかじめ明定化することも検討されています。
- 柔軟な働き方に対応しつつも、「休日の明確性」を維持するための手法設計(例:シフト決定時点で法定休日を記載)も論点となっています。
実務インパクト・留意点
- 就業規則や勤務規程の改定が必要です。特に休日制度が柔軟な企業では、「法定休日=毎週土日」といった単純な定義ではなく、シフト・変形勤務対応型の定義が求められます。
- 勤務表・シフト表を作成するプロセスで、法定休日の特定を明示する運用設計が必要です。例えば「当月の法定休日は〇日・〇日…」というカレンダーをあらかじめ提示・共有する、というような運用改善が考えられます。
- 勤務データ・休日データを管理する勤怠システム・給与システムの仕様変更を検討する企業も出てくるでしょう。休日労働割増賃金の対象判断が明確になる分、誤支払リスク・是正対象になる可能性があります。
- 労働者側としては、「どの日が法定休日か」が事前に明示されることで、休日取得・休暇取得・出勤判断における透明性が高まります。安心感につながる反面、シフトの変更・休日の振替が増える職場では混乱を防ぐための周知・説明も重要です。
3.勤務間インターバル制度の義務化
第3の検討案は、勤務と勤務の間に一定の休息時間(インターバル)を設ける「勤務間インターバル制度」の義務化です。
背景と意義
- 長時間労働・深夜労働・連続勤務が増える中、十分な休息を確保し、労働者の健康・安全を守る必要性が高まっています。
- 例えば、前日深夜帰宅後、次日朝早く出勤するなど、勤務間が短くなるケースがあり、これが疲労蓄積・事故リスク・健康リスクにつながる可能性があります。
- 欧米などでは勤務間インターバルの規定があり、こうした制度設計の方向性を受けて、日本でも義務化検討が進んでいます。
検討内容
- いくつかの報道によれば、「退勤から次の始業まで11時間以上の休息」などが目安として示されています。
- 義務対象となる事業場・業種・働き方(交替制・シフト勤務・深夜勤務者)などの整理が必要です。
- 制度導入にあたっては、勤務設計・シフト設計・交替制の見直し、出勤前の休息管理やシステム対応が不可避となります。
実務インパクト・留意点
- 深夜勤務・泊まり勤務・交替制勤務を行う事業所では、シフト設計の見直しが急務となります。例えば、終業後に十分な休息時間を確保できるよう勤務パターンを調整する必要があります。
- 勤怠管理システム、出勤・退勤時刻の記録・休息時間の確認プロセスなど、運用面では新たな手法が必要となるでしょう。
- 企業は「インターバルを確保できない勤務パターン」が生じていないか、実態調査を早めにすることが望まれます。
- 労働者側も「連続勤務・休息不足」が制度上リスクであるという認識が高まるため、自身の勤務形態・休息時間について関心を持つ必要があります。
4.有給休暇取得時の賃金算定方法の見直し
第4の検討案は、年次有給休暇を取得した際の賃金算定方法を、より厳格に「所定労働時間働いた場合に支払われる通常の賃金(通常賃金)」を基準とする方向への見直しです。
背景と意義
- 有給休暇は、労働者が休息・私生活を確保する重要な権利です。取得促進・安心して休める環境整備が求められています。
- しかし、休暇取得時に賃金算定の扱いがあいまいなまま運用されている事業場もあり、例えば代替休日制度や前日・後日の勤務状況により賃金が変わるといったケースがあります。
- 「有給休暇を取得しにくい」「取得しても賃金が不利になる」といった実態が、働き方改革・休暇制度改革の観点から問題視されています。
- こうした背景から、有給休暇取得時の賃金保障を明確にすることは、労働者の休暇取得促進・健康確保・ワークライフバランスを支える上で重要な施策です。
検討内容
- 有給休暇取得時の賃金を「通常賃金」と同一レベルとすることを原則とする方向が示されています。例えば「休暇前の所定労働時間を満たす勤務をしたときに支払われる賃金」を基準とするという考え方。
- 取得日数・計算基礎・割増賃金の扱い・代休・振替休日制度との関係など、制度設計上の整合性が検討されています。
- 取得促進策・企業における取得実績管理・従業員への周知・取得しやすい職場風土づくりもセットで論じられています。
実務インパクト・留意点
- 企業側は、有給休暇取得時の賃金計算ルールを見直し、就業規則・給与規程の改定を行う必要があります。例えば「有給休暇取得時の賃金=通常の所定労働時間賃金」という明示化が必要となるでしょう。
- 給与計算システム・勤怠システムで取得日数・基準賃金・割増賃金の自動計算が正しく行われているかを早期に検証することが望まれます。
- 労働者側としては、有給休暇を安心して取得できる職場ルール・制度整備が進むことになりますが、休暇申請・取得実績・賃金の確認など、自身の休暇取得状況を把握しておくと安心です。
- また、企業には取得促進・休暇取得状況のモニタリング・休暇取得時の支援体制(代理勤務者の確保・業務調整など)が求められます。
5.副業・兼業者に対する割増賃金の通算制度の見直し
第5の検討案は、複業・副業が増える中で、同一事業主ないし複数事業主にまたがる労働時間通算・割増賃金の取り扱いを見直すというものです。
背景と意義
- 働き方改革・デジタル化・雇用形態の多様化に伴い、副業・兼業をする労働者が増加しています。こうした状況下で、複数の事業所で働く際の労働時間通算・時間外・休日労働・割増賃金の対象範囲等に実務上の課題があります。
- 例えば、A社での勤務が終わってからB社で勤務するというケースにおいて、各社での労働時間を合算して時間外労働の対象とするか否か、という判断があいまいなまま運用されていることがあります。
- 労働者の実働時間・健康管理の観点から、通算制度を明確にすることは、過重労働防止、働き方の透明化という観点から重要です。
検討内容
- 報告書等では、「労働時間の通算制度を同一の事業主に限定する」方向が示されています。つまり、複数事業主間での通算適用を除くという可能性があります。
- 割増賃金の算定基礎・通算対象となる時間数・兼業者がいることを前提とした勤務管理・契約上の整理などが論点となります。
- 兼業・副業者に対する割増賃金のルール明確化、就業規則・雇用契約書等の整備、副業ガイドラインの整備・企業間の労働時間把握の整備も検討されています。
実務インパクト・留意点
- 企業側では、副業・兼業を認めている場合には、契約・就業規則・ガイドラインの見直しが必要です。例えば、「他社での勤務時間も通算対象とはせず、あくまで本社の勤務時間管理において通算を適用する」などのルール整備が求められます。
- また、勤怠管理・兼業者管理・労働時間把握の仕組みを整える必要があります。兼業・副業を許可する制度設計をしている企業では、時間外労働・休日労働・割増賃金の対象となるか否かを明示することが重要です。
- 労働者側では、兼業・副業を行う際に「どの勤務時間が本業・副業か」「通算対象か否か」を含めて契約内容をしっかり確認することが求められます。
- 通算対象から除外されることで、労働時間が短く見える可能性もあるため、実働時間・健康状態の自己管理も今まで以上に重要となります。